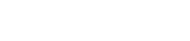

デジタルとリアルが溶けた世界を生きる、
人類の新・存在様式
ホモ・サピエンスからメタ・サピエンスへ。
Homo=同質な(とされる)存在から、
Meta=より多様で高次な(であるべき)存在へ。
デジタルとリアルが溶け合ったこの世界から、
新しい人類の行動原理が生まれつつある。
これは「進化」なのか?
新しい「人類」の誕生なのか?
メタ・サピエンスは暮らす。
移動する。食事する。
メタ・サピエンスは友情を育む。
共感する。恋をする。
メタ・サピエンスは社会をつくる。世界をもつ。
メタ・サピエンスは、わたしたちの新しい
「行動原理Principle」であり
「存在様式Being」かもしれない。